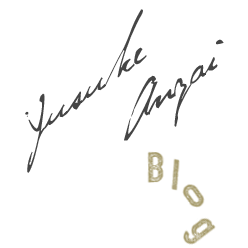人生とは選択の連続。分岐点に差し掛かったときに、右へ行くか、左へ行くかで学びが変わる。僕も多くの分岐点を経て生きてきた。ざっと思いだしてみてもいくつもの思い出が頭に浮かぶけれど、その大半が異性関係だったりするのが僕の程度のほどを表している。もっとこう、大きな契約を持ちかけられて迷った話だとか、国家の未来がかかるような選択だったりすれば格好もつきそうなもんだけど、こればかりは仕方が無い。で、いくつか思い浮かぶ異性関連の分岐点のなかでも最大のもの、今でもたまに思い出してはもやもやしているあのシーンのことを書いてみることにする。人間、歳をとると恥という感覚が薄れるもんで。
中学生の頃、好きな女の子がいた。仮にXさんとしよう。そのXさん、たぶん僕のことも好きだったと思う。というか、好きだった。お互いに好きだったんだけど、なぜか僕は「高校生になるまでは彼女は作らない」という、今思えば謎な誓いをたてていたので、Xさんだけでは無く、誰に対してもそんな方向には事を進めなかった。でもなんつーか、これは本人たちにしかわからないことだと思うけど、常にこう、意識しあっていたというか、そんなモヤッとしたものに支配された中学時代だった。
中学校を卒業した春休み、そのモヤッとした気持ちのまま高校に進学するのもアレだなという思いになり、思い切ってXさんに手紙を書くことにした。「好きでした」なんてことは書かない。というか書けない。恥ずかしいから。「いつも見ていました」と書いた。それでもやはり恥ずかしいので、書いた手紙をそのまま封筒に入れるのでは無く、その手紙を筒状にした紙で巻き、その紙に「かくかくしかじかだから、その気持ちであれば開けて読んでください。」みたいなことを書いて、封筒に入れ、ポストへ投函した。数日後、Xさんから手紙が届いた。そこには「私もいつも見ていました」と書いてあった。こたつの前でガッツポーズをしたことを覚えている。
Xさんから手紙をもらってからも、僕は何ら行動を起こさなかった。いや、正確に言うと、どうしていいのかが分からなかった。違う高校に進んだので会うことは無いし、これからのことを話しあうためにまた手紙でやりとりをするのもちょっと…と思えるし、そもそも毎日のように部活があるので現実的では無いし…。
季節は過ぎて、2月。いつものようにバスに乗り、乗り換えのために途中の停留所で降り、学校方面へと向かうバスの列に並びなおして顔を上げると、道路の反対側にXさんが立っていた。高校の制服を着て、少し化粧をして、手には小さな紙袋を下げたXさんだった。いや、正確に言うと、僕にはXさんに見えた。たぶんXさんだったと思う。驚きと恥ずかしさで僕は顔を背けてしまった。そして、横に立っていた通学仲間のTくんに向かってマシンガンのように無駄話を浴びせた。Tくんは「う、うん…」という感じでXさんのいる方向をチラ見しながらも僕のトークに付き合ってくれた。その日はバレンタインデーだった。
最低な人間だなと思う。驚きと恥ずかしさから来る咄嗟の行動だったとはいえ、何十人もの人間が並んでいるバス停の向かい側にひとり立って僕を待ち続けていたであろうXさんは、僕の何十倍も恥ずかしかったと思う。僕は心の中の想いとは真逆の行動しか取れなかった。それを「思春期」という言葉で片づけてしまって良いものなのかは分からないけれど、最低であることは間違い無い。
「タイムマシーンがあったらどうしたい?」なんてことを言うけれど、あの日には戻ってみたいなとは思う。戻ってどうするかなんてことは考えていないし考えたく無い部分もあるけれど、とにかく、一度、戻ってみたくはある。現状に不満があるとか、そういうことでは無く。